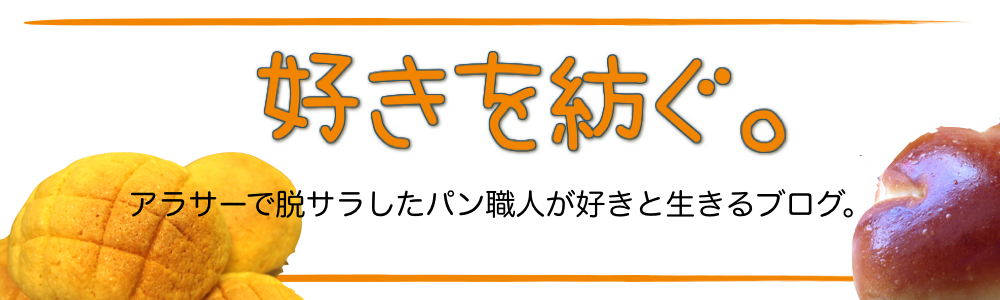パン屋さんを開業する方や経営している方で、
- 一般的な原価率ってどのくらいなんだろう?
- 原価率の具体的な計算方法はどうしたらいいの?
と思う方もいらっしゃると思います。
結論からいえば、次のとおりです。
- 原価率とは、売上のうち原価の占める割合
- パン屋さんの原価率の目安は30~35%ほど
- 原価率は、パン屋さんの経営状態の良し悪しを知る指標の1つになる
- 原価率に影響を与えるのは、パンの種類、材料、そして販売価格の3つ

僕も実際にパン屋さんで働くまでは、まったく知りませんでした。
この記事では、10年近くパン職人として仕事をしている僕が、パン屋さんの原価率について解説します。
この記事を読めば、
- 原価率とは
- 原価率の計算方法
- 原価率が大切な理由
- パン屋さんの一般的な原価率
- どういったものが原価率に影響するのか
といったことの理解が進み、パン屋さんの原価率についてマスターできるようになるでしょう。
目次
原価率は、売上のうち原価の占める割合のこと
原価率とは、売上のうち原価の占める割合のことです。
式で書くなら、次のようになります。
原価率(%) = 原価(円) / 売上(円) * 100
たとえば、
- 売上:100万円
- 原価(材料を買ったお金):20万円
であれば、
原価率 = 20/100*100 = 20%
つまり、原価率は20%になります。

ここまでは簡単ですね。
商品1つあたりの原価や原価率を計算する方法
商品1つあたりの原価率を計算する場合は、次のようにします。
【商品1つあたりの原価率の計算方法】
- 商品1つあたりの、それぞれの材料の重さを計算する
- それぞれの材料について、1g当たりの原価を計算する
- 1.と2.をかけて、商品1つあたりのそれぞれの材料の原価を計算する
- 3.で計算した値をすべて合計すると、商品1つあたりの原価が計算できる
- 4.を売値で割ると、商品1つあたりの原価率が計算できる
こう書くと難しそうですが、具体例があるとそれほど難しくないと思います。
「パン屋における商品1つあたりの原価率を計算する方法」では、具体例を挙げてさらに詳しく解説しています。
原価率が大切な理由は、経営状態を示す指標の1つになるから
原価率を把握するのが大切なのは、それが経営状態の良し悪しを知る材料になるからです。
ざっくりいえば、次のようなイメージです。
- 原価率が低い場合
- →売上から材料費・人件費・家賃などを引くと、お金が残りやすい
- つまり、利益がでやすい
- 原価率が高い場合
- →売上から材料費・人件費・家賃などを引くと、お金が残りにくい
- つまり、利益がでにくい(赤字になりやすい)

もちろん、経営状態の良し悪しには、人件費・家賃・借り入れの返済といった数字も大きく関わってくるので、あくまで原価率は指標の1つとして考えると良いと思います。
では、パン屋さんの一般的な原価率をみていきましょう。
パン屋さんの一般的な原価率の目安は約30~35%
パン屋さんの一般的な原価率は約30~35%です。
これくらい抑えられていれば、パン屋さんの中では一般的な商売をしているといえるでしょう。
もし大きく上回っている場合は、上で述べたように「利益がでにくい」状態である可能性があります。

もちろん、これはあくまで目安です。たとえ原価率が35%以上でもしっかり利益がでているお店もあります。
原価率に影響を与えるのは、パンの種類、材料、そして販売価格の3つ
原価率は、次のもの影響を受けやすいといえるでしょう。
- 作るパンの種類
- 使う材料
- 販売価格
どんな種類のパンを作るかによって、原価率は変わる
作るパンの種類は、原価率に大きく影響します。
たとえば、食事パンは原価率が低くなりやすいです。
なぜなら、食事パンは生地に具を入れず、そのまま成形したものだからです。
具というのは、
- あんこ
- クリーム
- ソーセージ
といったものです。これらはどうしても原価が高くなりがちです。

そのため、具が入っていることが多い菓子パンや惣菜パンは、原価率が高くなりやすいです。
食事パンの具体例としては、
- 食パン
- バターロール
- バゲット
- カンパーニュ
などになります。
食パン専門店が流行っているのも、原価率を抑えやすいのが理由の1つだと思います。
高級な材料なら原価もあがり、原価率も高くなりやすい
原価率は、材料の品質にも影響を受けやすいです。
- 品質の高い、高級な材料を使う
- →原価が高いので、原価率は高くなりがち
- 品質が普通の、お手頃価格の材料を使う
- →原価が安いので、原価率を抑えやすい
もちろん、販売価格をいくらにするかによって原価率をコントロールもできます。
しかし、一般的な価格より高くする場合は、
- POP、販促物で価値を示す
- 直接、お客さんと話をしてアピールする
といった、納得してもらう工夫が必要になるでしょう。
販売価格を変えれば、それに連動して原価率も変わる
上でも述べたとおり、原価率は販売価格でコントロールできます。
基本的な考え方としては、次のようになります。
- 原価率を下げたい
- →価格を上げる
- 原価率を上げたい(基本無いと思いますが…)
- →価格を下げる
つまり、
- 目安となる原価率を先に決めておく
- それに合わせて価格を決める
という手順をとれば、原価率が目安から大きく離れてしまうことはありません。
しかし実際にお店を経営すると、
- 原価率は適正だけど、他のお店の価格と違いすぎて全然売れない
- 原価率は適正だけど、大きさの割に高すぎてお客さんの反応が悪かった
- 自分のお店の目玉商品なので、少し安めに設定して数を売れるようにしたい
といったようなことが日々、起こります。こういった場合は原価率にこだわりすぎないほうが良いでしょう。
原価率はあくまで目安。
実際の状況に合わせて価格と原価率のバランスをとりながら、コントロールしていくことが大切です。
関連記事:パン屋さんにおける商品の価格を決めるためのポイント
原価率をマスターして、パン屋さんの開業・経営に活かそう
この記事では、パン屋さんの原価率について、目安や考え方のポイントを解説しました。
結論からいえば、次のとおりです。
- 原価率とは、売上のうち原価の占める割合
- パン屋さんの原価率の目安は30~35%ほど
- 原価率は、パン屋さんの経営状態の良し悪しを知る指標の1つになる
- 原価率に影響を与えるのは、パンの種類、材料、そして販売価格の3つ
原価率について理解すれば、パン屋さんの開業や経営にも役立つこと間違いないでしょう。
ぜひ、理解を深めてくださいね。
【PR】パン・お菓子作りの材料・器具を買うなら【cotta】
パンやお菓子の材料を買おうと思っても、
- 近くに材料を売っているお店がない
- 100均やスーパーに売っている材料では物足りない
- 忙しくてわざわざ買いに行く時間がない
ということがあって、不便を感じている方も少なくないと思います。
実際、僕が住んでいるのも田舎なので、小さなパン屋を始めるにあたって本格的な材料が必要でしたが、良いお店が見つからず困っていました。
こういった不便を解消してくれるのが、プロも愛用!安心安全の材料と豊富な品揃えが自慢の【cotta】です。
cottaを利用すれば、
- 専門店で売っているような本格的な材料が手に入る
- 大容量で割安の材料が手に入る
- ショッピングモールや百貨店などを歩き回る必要がない
- 店舗まで買いに行く必要なく、自宅で受け取ることができる
- 条件を満たせば送料も格安
といった、たくさんのメリットがあります。
僕も実際に、パン屋さんの材料や器具を仕入れるのに使っていて本当におすすめなので、ぜひお試しください!