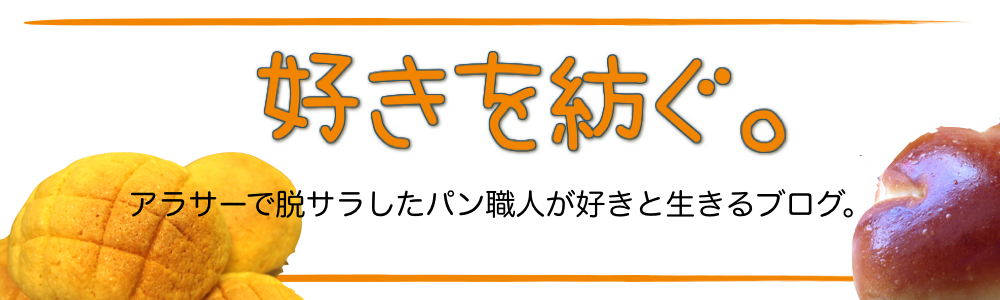原価率って具体的にどうやって計算したらいいか分からない、という皆さん。
この記事では、パン屋さんにおける商品1つあたりの原価率の計算方法を解説します。
結論からいえば、次のようになります。
【商品1つあたりの原価率の計算方法】
- 商品1つあたりの、それぞれの材料の重さを計算する
- それぞれの材料について、1g当たりの原価を計算する
- 1.と2.をかけて、商品1つあたりのそれぞれの材料の原価を計算する
- 3.で計算した値をすべて合計すると、商品1つあたりの原価が計算できる
- 4.を売値で割ると、商品1つあたりの原価率が計算できる

正直、↑のように言葉で書くと分かりにくいですよね。
でも大丈夫、この記事では、食パンを例にかなり具体的に手順を解説しています。
この記事を読めば、きっとパン屋さんの原価率の計算をマスターすることができるでしょう。
↓「原価率とは?」「目安は?」という方は先にこちらをどうぞ。
関連記事:知らないとまずい?パン屋さんにおける原価率の目安や考え方のポイントを解説します
目次
原価率は原価を売上で割ったもの
原価率は原価を売上で割ったものなので、式は次のようになります。
原価率(%) = 原価(円) / 売上(円) * 100
売上が100円、原価が20円なら、原価率は、
原価率(%) = 20 / 100 * 100 = 20%
となります。ここまでは簡単ですね。

では具体的に、商品1個あたりの原価を計算してみましょう。
食パン1斤の原価率を計算してみよう。
商品1個あたりの原価率を計算する場合は、
- その商品のレシピ
- 材料の価格
をもとに、計算していきます。

今回は、食パン1斤(販売価格400円)を例にして、説明します。
まずは食パンのレシピを確認しましょう。
ベーカーズパーセント(小麦粉を100としたときの割合)はこちらで考えます。
| 材料 | ベーカーズパーセント |
| 小麦粉 | 100 |
| 砂糖 | 8 |
| 塩 | 2 |
| イースト | 2 |
| 水 | 68 |
| バター | 4 |
※分割は200g、2斤型に200g×4を詰めるとします。
食パン1斤あたりの、材料の重さを計算しましょう。
今回は2斤型に200g×4=800gの生地を使います。
なので、食パン1斤分の生地重量はその半分になります。
800g / 2 = 400g
また先ほどのレシピから、小麦粉100gあたりの生地重量は、次のようになります。
100+8+2+2+68+4 = 184g
この2つの比を計算すると、
400g / 184g = 約2.17
となります。
そしてこの比を、ベーカーズパーセントに掛けることで、食パン1斤あたりの各材料の重量を計算することができます。
計算すると、次のようになります。
| 材料 | ベーカーズパーセント | 食パン1斤あたりの重さ |
| 小麦粉 | 100 | 100*2.17=217g |
| 砂糖 | 8 | 8*2.17=17.36g |
| 塩 | 2 | 2*2.17=4.34g |
| イースト | 2 | 2*2.17=4.34g |
| 水 | 68 | 68*2.17=147.56g |
| バター | 4 | 4*2.17=8.68g |
表①

食パン1斤あたり、それぞれの材料が何グラム使われているか、計算することができました。
次に材料の内容量と価格を確認し、材料1gあたりの原価を計算しましょう。
材料の金額(円)を重さ(g)で割ると、1gあたりの原価が計算できます。
例えば小麦粉なら、1kgを1000gに直して計算するので、
500(円) / 1000(g) = 0.5(円/g)
となり、これを全部の材料で同じように計算すると、次のようになります。
| 材料 | 内容量 | 価格 | 材料1gあたりの原価 |
| 小麦粉 | 1kg | 500円 | 500/1000=0.5(円/g) |
| 砂糖 | 1kg | 300円 | 300/1000=0.3(円/g) |
| 塩 | 500g | 200円 | 200/500=0.4(円/g) |
| イースト | 20g | 400円 | 400/20=20(円/g) |
| 水 | (今回は0円) | 0(円) | |
| バター | 150g | 450円 | 450/150=3(円/g) |
表②
ここまでの数値を使って、食パン1斤の原価を計算します。
表①と表②の数値を掛け合わせることで、食パン1斤に含まれる各材料の原価を計算することができます。
小麦粉なら、次のように計算します。
217(g) * 0.5(円/g) = 108.5(円)
これをすべての材料について計算すると、次のようになります。
| 材料 | 食パン1斤あたりの材料の原価 |
| 小麦粉 | 217*0.5=108.5(円) |
| 砂糖 | 17.36*0.3=5.21(円) |
| 塩 | 4.34*0.4=1.74(円) |
| イースト | 4.34*20=86.8(円) |
| 水 | 147.56*0=0(円) |
| バター | 8.68*3=26.04(円) |
表③
この表のすべての数字を足すと、食パン1斤の原価が計算できます。
108.5 + 5.21 + 1.74 + 86.8 + 0 + 26.04 = 228.29円
つまり、食パン1斤の原価は約228円、ということになります。
最後に原価率を計算しましょう。
さて、ここまできてやっと、原価率を計算できます。
食パン1斤の原価が約228円、販売価格が400円なので、
228 / 400 * 100 = 57%
この食パンの原価率は、53.5%となります。

実際には、こんなに原価のかかっている食パンはあまり無いでしょう。
原価率を計算して、日々の経営の参考にしよう
この記事では、パン屋さんにおける商品1つあたりの原価率の計算方法を解説しました。
方法は、次のとおりです。
【商品1つあたりの原価率の計算方法】
- 商品1つあたりの、それぞれの材料の重さを計算する
- それぞれの材料について、1g当たりの原価を計算する
- 1.と2.をかけて、商品1つあたりのそれぞれの材料の原価を計算する
- 3.で計算した値をすべて合計すると、商品1つあたりの原価が計算できる
- 4.を売値で割ると、商品1つあたりの原価率が計算できる
1つ1つの商品について原価率を計算すれば、
- 価格を決めるための指標になる
- 使用する材料を選ぶのに役立つ
といったメリットがあります。
具体的にいえば、次のようなことです。
- ある商品の原価率が、目安と比べて高すぎる
- →価格をもう少し上げる
- →材料をもう少し安いものにする
すべての商品に対して一律の原価率である必要はありません。
お店全体のバランスを考えて、原価率を参考にしながら、価格や材料を検討してみてはいかがでしょうか。
(↓価格の決め方についてはこちら。)
関連記事:パン屋さんにおける商品の価格を決めるためのポイント
【PR】パン・お菓子作りの材料・器具を買うなら【cotta】
パンやお菓子の材料を買おうと思っても、
- 近くに材料を売っているお店がない
- 100均やスーパーに売っている材料では物足りない
- 忙しくてわざわざ買いに行く時間がない
ということがあって、不便を感じている方も少なくないと思います。
実際、僕が住んでいるのも田舎なので、小さなパン屋を始めるにあたって本格的な材料が必要でしたが、良いお店が見つからず困っていました。
こういった不便を解消してくれるのが、プロも愛用!安心安全の材料と豊富な品揃えが自慢の【cotta】です。
cottaを利用すれば、
- 専門店で売っているような本格的な材料が手に入る
- 大容量で割安の材料が手に入る
- ショッピングモールや百貨店などを歩き回る必要がない
- 店舗まで買いに行く必要なく、自宅で受け取ることができる
- 条件を満たせば送料も格安
といった、たくさんのメリットがあります。
僕も実際に、パン屋さんの材料や器具を仕入れるのに使っていて本当におすすめなので、ぜひお試しください!